さて、1級試験についてです。
別のページでも触れましたが、1級の筆記試験は記述式であり理解力を求められるため、レベルが桁違いに上がります。
2級の合格率が約90%なのに対して1級の合格率は15%前後であることが全てを物語っています。
イメージとして、教本の1級の範囲(p48〜p90)を隅から隅まで覚えて最低限の合格ライン(80点)だと思ってください。
ここでは、あくまでも私が経験してきた勉強法をお伝えしますが、全てをそのまま参考にする必要はないと思っています。私の勉強法はただの根性論なので(笑)
2級と同じように、教本の内容をノートに何度も書き写して暗記して、ひたすらアウトプットをしていくというのを繰り返すだけです。
もっといい勉強方法があれば全然そちらを実践していただいて構いませんので。
とはいえ、筆記試験は90点・実技試験(再試験)は85点を獲得しているという保証のうえで、なるべく詳細に書いていきます。
まず、筆記試験について。
勉強スケジュールは以下の通りです。
- 4月〜 学習開始(教本の書き写し)
- 5月〜 学習サイトを利用したアウトプット
- 5月末:事前講習会
- 6月〜カンニングペーパー作成、アウトプット、過去問
- 7月初旬:1級試験日
といった感じで、約3ヶ月間ガッツリ勉強しました。
見方を変えると、4月まではほとんど勉強していませんでしたが、4月に入ってから本気を出し始めて合格まで漕ぎ着けました。
といっても、勉強期間はがっつり根詰めしたわけではなく、平日は2〜3時間、休日は5〜6時間の勉強を欠かさず行ってきただけなので、自分としても無理なく継続できたのかなと思っています。
勉強内容についても詳しく説明します。
2級の学習時は教本の内容をノートに転記して暗記する方法のみで合格できましたが、1級を受験するにあたってもいい方法が思いつかず、ひとまず同じように教本の内容をそのまま転記して、用語や雰囲気に慣れることだけを考えました。
とはいえ、2級と違って教本の範囲が広くなっているので(約40p)、全てを転記するのは流石に難儀いと感じました。
なのでまず、教本の中でも暗記が必要と思われる項目だけをピックアップして、あとで暗記帳として繰り返し見れるように、ノートに丁寧に記載しました。
その時の項目は、
- コーヒーの伝播と歴史
- 品種
- 生豆の成分
- 成分の定義
- 焙煎による成分の変化
になります。
これだけでもかなり覚えることはありますが、実際の範囲はまだまだあります。ひとまずこの作業を1週間ほどで完了させました。
また、なんとなく事前講習会までに教本の内容を一通り把握しておきたいと思っていたところ、以下のサイトを見つけました⇩⇩
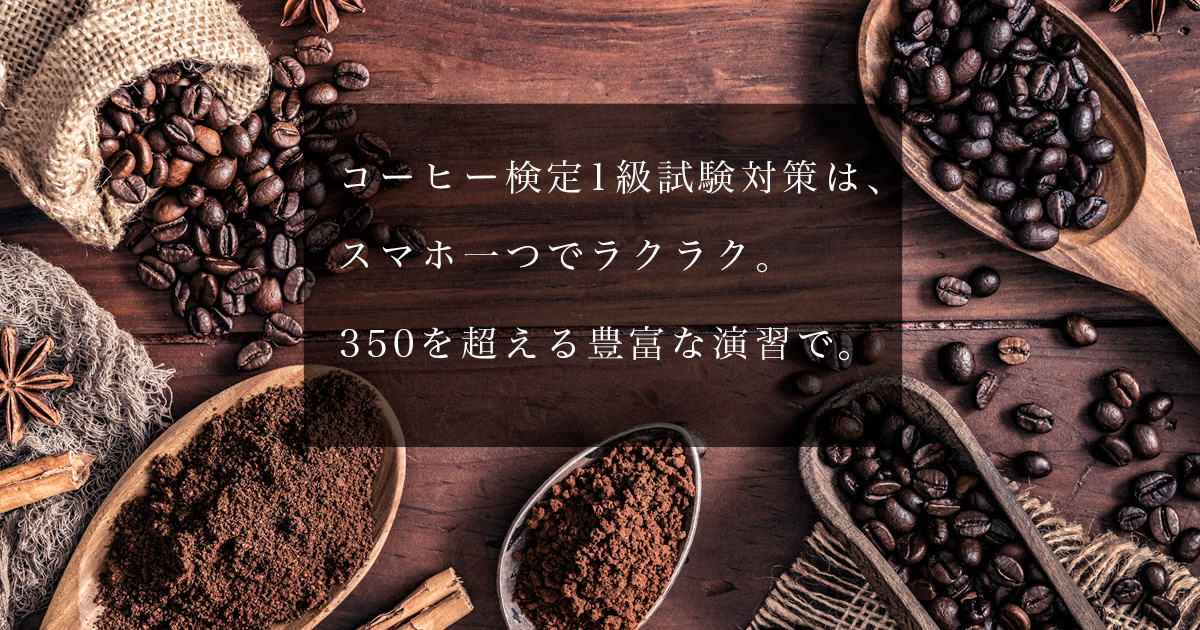
月額料金はそれなりにかかりますが、教本の内容が全て網羅されていて、1文章ごとに1問1答方式で学習ができるので、かなりおすすめです。私自身も受験日までフル活用させていただきました。
隙間時間などで何度も繰り返し学習することで自然と覚えることができますので、月額分の価値は十分にあるかと思います。
(余談ですが、コーヒーインストラクター1級について詳細に書かれているサイトは上記のものしか見つけられませんでした。もっとあってもいいのではないかと思い、当サイトを作るきっかけになったのでした。)
といった感じで、このサイトを活用して事前学習までに教本の内容を一通り把握することができました。
なお、この段階ではまだ教本の内容を一言一句完璧に覚える必要はないと思います。試験範囲全体をなんとなく把握できる程度(学習サイトでいえば70〜80%くらい)で十分です。
*
そして迎えた事前講習会。
1級の講習会は、1日目に筆記と2日目に実技で2日間に亘ってガッツリ行われます。
1日目の筆記は、2級と同じように教本の内容と捕捉事項の説明になります。寝ちゃダメですよ。
ただ、2級と明らかに違うのは、講義を聴くだけでは理解が難しいところです。それだけ内容が専門的でレベルが上がっているということです。
その点においては、教本で予習をしておいて正解だったなと、今振り返ってしみじみと感じています。
また、教本に記載がない講師からの捕捉事項も出題される可能性が十分あります。私が聞き取った範囲は学習ページで記載したいと思いますが、特に注意して聴くようにしましょう。
2日目の実技について。
前日の座学と違い、作業が基本になります。2級試験時に貰ったカッピングスプーンとコップを必ず持参しましょう。
内容は主にカッピングと焙煎豆の外観識別になります。カッピングの基礎から風味の特徴の説明、焙煎豆の外観の特徴や見極め方などを細かく解説していただけるので、その日だけで十分理解ができます。
といった感じで、実技に関しては特に予習は必要ないと思いますので、その分講義の内容をしっかり覚えておきましょう。
なお、講義で使用した標本は全て持ち帰ることができますし、その後の勉強にも役立つものになります。想定よりもかなり量が多いので、最低でも20ℓ程度の持ち帰り袋を用意しておくと間違いないです。
*
さて、事前講習会が終わり、試験まであと1ヶ月となりました。
そこから取り組んだことは、とにかくひたすらシンプルにインプットとアウトプットの繰り返し。
まず取り組んだのは、教本の内容のノート転記です。といっても、講義前のような丁寧なものではなく、殴り書きで汚くてもいいから全ての内容を書きながらイメージしていくという作業です。
正直、この作業はそこまで頭に入ったという実感はありませんでしたが、何も取り組まないよりはよっぽどいいですし、試験時には「これだけ取り組んだのだからきっと大丈夫」という自信にもつながりました(まさに根性論!)。
また、同時並行で上記の学習サイトでも繰り返し勉強をしました。
朝の出勤前の1時間は学習サイトで勉強して、仕事終わりの1時間〜2時間は教本のノート転記の作業といった感じで毎日を過ごしていました。
私の場合、朝に勉強した方が頭に入る(気がする)のと、仕事前に書き作業をするのが億劫だったので、手間のかからない学習サイトの勉強を朝に行い、学習効率が低めの仕事終わり時間をノート転記に充てました。
ノート転記自体は、1日2時間前後の作業時間で約2週間ほどで完了しました。
まあでも、この点に関しては個人差があると思いますし、そもそもノート転記作業が必要ないという方もいると思いますので、その辺りは各人にお任せします。
次に取り組んだのは、個人用の過去問集の作成です。
と言いましても、ネットに転がっている過去5年間ほどの過去問の内容を、そのままエクセルに移して体裁を整えただけなのですが(笑)
本当は皆さま向けに公開したいところなのですが、権利云々に関わってくると思うので、申し訳ございません…
この時点で、試験日まで残り2週間ほど。
やれると思うことは一通りしたつもりでしたが、やはりまだ不安は拭えませんし、知識の定着化という点ではまだ自信がありませんでした。
そこで、最後の悪あがきで取り組んだのが、カンニングペーパーの作成です。
これまでのような教本の内容を全てそのまま書き込むものではなく、要点だけを箇条書きして分かりやすくまとめたものになります。
最初からそうすればいいじゃんとも思えますが、初期の何もわからない状態ではどこが要点なのかも分からないですし、ある程度全体像を把握しているからこそ大事な箇所が分かってきます。
何度も書いているように、教本の中からどの部分が出てくるか分かりません。要点だけを抑えたり”ヤマを張る”といったことは控え、無駄だと思っても時間をかけてしっかり覚えて理解を深めることを考えましょう。
あとはもう、試験までひたすら暗記とアウトプットの繰り返しです。
編集中。。。
