主に、コーヒーの生産国や収穫時期を学ぶブロックと、コーヒーの栽培からの流れを学ぶブロックになります。
早速、暗記する項目が多いエリアになりますが、そこまで難易度は高くありません。しっかりじっくりと覚えていきましょう。
また、「ICO(国際コーヒー機関)に登録されている輸出国は約45ヶ国、ICO非加盟生産国を加えると約60ヶ国・・・」といった数値的な部分もしっかり覚えましょう。
1.世界のコーヒー生産国
品種 p20
そもそもコーヒーにはたくさんの品種があり、教本p20にもいくつか記載されていますが、実際の2級の試験においては、
・アカネ科コフィア属に属する熱帯植物であること
・全生産量の60%程度を占めるアラビカ種と約40%を占めるカネフォラ種があること
を覚えておけば問題ないです。
なお、事前講習会において講師から品種ごとの適切な栽培条件について説明があるかと思うので、しっかり聞いてメモをとりましょう。
コーヒー生産国と収穫時期 p21
主に赤道を挟む南北約25度の「コーヒーベルト」と呼ばれる地帯で栽培されています。
教本に記載されている白地図の国名と位置は必ず覚えましょう。高確率で出題されます。
収穫時期(収穫ピーク)については、先述の白地図が分かっていると覚えやすいかと思います。
私の場合、赤道付近のインドネシア・コロンビア・ケニアは年2回、北半球のグアテマラ・ベトナム・エチオピアは下半期、南半球のブラジル・タンザニアは上半期(北半球は下半期、南半球は上半期)といった感じでイメージして覚えました。
収穫量 p22
主なデータは教本のとおりですが、記載にもあるように各国の生産量と日本への輸出量は比例していません。
生産量の上位と日本への輸出量の上位国は、4位までは同じですが(1位:ブラジル、2位:ベトナム、3位:コロンビア、4位:インドネシア)、5位はそれぞれ異なり、生産量の5位はエチオピアに対して日本への輸出量の5位はグアテマラになります。
その辺りがごっちゃにならないよう気をつけてください。
なお、生産量の細かい数字を覚える必要はありませんが、生産量及び輸出量の上位国は覚えておきましょう。
2.生豆ができるまで
一連の行程である「栽培→収穫→精選→選別」という流れは、本試験のみならずコーヒーを知る上で基礎的な知識になるので、ぜひ覚えてください。
また、コーヒーチェリーの構造も非常に重要になってきます。
各部位の名称や構造を、記載の図を参考にイメージをつけておきましょう。
精選 p22〜
果実(コーヒーチェリー)から生豆を取り出すにあたっての一連の工程を「精選」といいます。
4つの主な精選方法は(非水洗式)(水洗式)(パルプドナチュラル)(スマトラ式)
どの方法を用いるかは(生産環境)(地理的条件)(気象条件)(マーケティング戦略)などによって決まる
といったように、覚える項目が比較的分かりやすいので、もれなく覚えましょう。
また、p23の精選工程の具体的な内容ももれなく出題されますので覚えましょう。
選別 p23
精選工程を経てできた生豆の大きさ・形・色などの外観を揃える作業を「選別」といいます。
選別工程はいくつかありますが、2級で学ぶ選別工程は(スクリーン選別)(比重選別)(比色選別)の3つになります。
また、(比色選別)には、目視で行う「ハンドピック」と、光の反射率の違いを利用する「電子選別」があります。
これらの選別工程から1つを選ぶというわけではなく、生産コストや商品規格などによって組み合わせて行います。
工程の手順としては(スクリーン選別)→(比重選別)→(比色選別)の順番になります。
なお、選別工程は生豆の大きさを揃えるための作業であり、異物を取り除く作業は精選工程の中で行われます(詳しくは1級の内容になります)。
〜fin〜

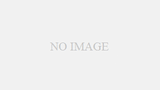
コメント