余談ですが、私は2級試験において減点した問題の内訳は、ほぼ全て格付けの部門です。さすがに規格などの細かいところまでは出題されないだろうと油断していたら、しっかり出題されました。
他の部門に自信があればいいですが、余裕があれば本項もしっかり覚えましょう。
1.格付けとは
「当初コーヒーは鑑定されることなく売られていたが、19世紀にニューヨーク・コーヒー定期取引市場が創設されたのを機にブラジル産コーヒーの格付けが始まった。そして、現在では各生産国で独自に格付けが行われている」(教本p24より抜粋)
表題のNo2やSHBなどという記号は、各国の格付けの結果を反映した格(グレード)を表しており、記号の付け方も国によって様々です。
2.主要生産国の格付け
教本にもあるように、格付けの方法に統一した国際基準はなく、各生産国の生産環境などによって独自に行われています。
とはいえ、主要生産国で見れば格付け方法は主に4つ(+格付けなし)に大別されるため、以下に記載の通り、まずは生産国と格付け方法を結びつけるように覚えましょう。
1)栽培地の標高による:中米各国、メキシコ
2)スクリーンサイズ(生豆の大きさ)による:コロンビア、ケニア、タンザニア
3)欠点数(タイプ)による:ペルー、エチオピア
4)スクリーンサイズと欠点数による:ブラジル、インドネシア、カリブ海諸国
5)格付けなし:イエメン
次に、格付けについて詳しく解説していきます。
1)栽培地の標高による
栽培された場所の標高によって格付けされていて、標高が高い方がグレードが高くなっています。
コーヒー栽培は、標高が高い方が昼夜の寒暖差があり、コーヒーチェリーがじっくり成熟することで総合的に味がよくなると言われています。
なので、実際に味をとったり見た目で判断されることなく、標高によって評価されています。
主に中米各国で採用されていますが、生産国によって規格が異なります。標高までは覚えなくていいですが、規格の大小(メキシコであれば、高グレードが”HG”で低グレードが”PW”)はしっかり覚えましょう。
2)スクリーンサイズによる
スクリーンサイズとは直訳すると網目の大きさのことであり、つまりは生豆の大きさで格付けされています。
主に赤道直下の国で採用されていて、サイズが大きい方が実が完熟していて味が良いという評価になります。
こちらも、スクリーンサイズの数値は覚えなくていいですが、規格の大小をしっかり覚えましょう。
コロンビアのみ、記号ではなく名称(エクセルソ・スプレモ、エクセルソ・UGQ)なので気をつけましょう。
3)欠点数による
生豆300gあたりの欠点数(未成熟豆など)によって評価されます。欠点数が少ない方が味が良いというのはイメージしやすいですね。
グレードが高い方から”グレード1”〜という企画になっているので、こちらも分かりやすいかと思います(実際の商品名には”G1”と表記されることが多いです)。
4)スクリーンと欠点数による
これが厄介でして、正直私も未だによく理解していませんので、ざっくり説明します。
なお、この評価方法は実際もっと複雑なようですが、教本に書いてある以上のことは出題されませんのでご安心ください。
【ブラジル・インドネシア(カネフォラ種)】
教本p25記載のスクリーンサイズを満たしたうえで、欠点数毎に規格が設定されています。評する基準が欠点数になっているので、欠点数が少ない方がグレードが高くなっています。
なお、インドネシアにおいてこの格付けをしているのはカネフォラ種であり、アラビカ種の場合は欠点数のみで評価しています(2級では触れられていないので覚えないで大丈夫です)。
【ベトナム(カネフォラ)、キューバ、ハワイコナ、ブルーマウンテン】
教本p25記載の「スクリーンサイズ 且つ 欠点数」つまりは両方を満たした場合で規格が設定されています。
スクリーンサイズも欠点数も数字が高い方がグレードが高いと評価されていますが、こちらも生産国によって規格の付け方がバラバラです。覚えるのがかなり大変ですが頑張りましょう。
〜fin〜

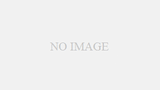
コメント