本項もまた、覚えることがたくさんあります。ちょっと大変ですが頑張りましょう!
さて、p26の冒頭にもあるように、近年は市場の二極化により、低価格で量販されるコーヒー商品が出る一方で、様々な付加価値がついたコーヒー商品も増えてきています。本項では、その付加価値がついた商品の種類について解説しています。
1.特定銘柄
コーヒーの商品名でよく見かける”ブルーマウンテン””マンデリン”などは、この特定銘柄にあたります。
教本の記載では「事実と異なったり、誇張されたりした広告により消費者が不利益を被らないように、事業者間の公平な競争によって消費者の自主的・合理的な商品選択に役立つよう、各業界がいろいろな商品について消費者の意見を採り入れている。」「その中で、実態に合った自主ルールを決め、消費者庁及び公正取引委員会がこのルールを『公正競争規約』として認定している。」「レギュラーコーヒー、インスタントコーヒーについては『全日本コーヒー公正取引協議会』がルール作りをおこなっており、定義を定めている。」とあります。
つまりは、それぞれの定義を満たしたコーヒーのみが特定銘柄の名称を名乗れるというニュアンスさえ理解していれば、一旦大丈夫です。
また『公正競争規約』『全日本コーヒー公正取引委員会』といった語句も覚えておきましょう。
なにより、表1-⑨の特定銘柄一覧は試験に出るので、名称と定義をしっかり覚えましょう。また、生産国の白地図も試験に出るので、教本p12〜の地図と照らし合わせて覚えると理解しやすいでしょう。
余談ですが、上記のようにあくまで日本国内の取り決めなので、海外でこの特定銘柄は通用しないようです。
2.農園指定のコーヒー、生産者組合のコーヒー
特定銘柄ほど目にすることは多くないですが、農園名のついた商品も多く流通しています(ブラジル ダテーラ農園など)。
教本p27の記載を要約すると、主に以下のように分類されます。
・数十軒以上の小農家のコーヒーが混ざったもの→小農家同士で生産者組合をつくり、組合員でお金を出し合い、新しい設備を購入して使用し、作業を共同で行うことで品質を高める。
・豊富な資金力、広大な農地を持った大農園で生産されることで、品質の均一性・設備投資・トレーサビリティといった付加価値がつけられる。
・小規模農園単体で、通常の輸出ロットの1/10程度の量の厳選した生豆を1ロットとしてオークションを行ない、風味や順位を付加価値としている。
暗記が必要な明確な語句はないですが、内容をしっかり覚えましょう。
3.認証コーヒー
商品のパッケージにマークがついたコーヒーが認証コーヒーにあたります。
各認証団体それぞれの独自の基準があり、それらの条件をクリアしたコーヒー商品に認証マークが付与されています。
特に、有機(オーガニック)・フェアトレード・バードフレンドリーなどは色んなコーヒーショップでもよく見かけるようになった気がします。
また、認証コーヒーは製造者だけでなく購入をすることで社会貢献ができるという点での付加価値があるのが特徴です。
教本p27にある認証コーヒーの名称と詳細をしっかり覚えましょう。
4.スペシャルティコーヒー
業界ではすっかり市民権を獲得しているスペシャルティコーヒー。世間一般的に一番分かりやすく影響力のある付加価値なのではないでしょうか。
とはいえ、コーヒーインストラクター検定ではスペシャルティコーヒーについて詳しく説明がありません。
教本p28に記載の通り、あくまで「日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)」の定義のみをしっかり覚えれば大丈夫です。
なお、詳しい説明を見たい人は、教本p138に記載がありますので参考までに。※試験には出ません

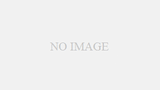
コメント