1.コーヒーの味を変える要因
前項のミルの説明でも触れましたが、コーヒーの味を変える要因はいくつもあり、同じようにコーヒーを淹れたつもりでも味が変わったと感じた経験は誰しもあると思います。
コーヒーの味を変える要因を理解することは、自分の好きな味を作り出せること・同じ味を安定して作り出せることに繋がります。
ここでは、味を変える要因を7つ解説していきます。なお、教本p32では6つですが、事前講習会の中で追加で1つ紹介されていますので、そちらも併せて記載します。
1)どんなコーヒーを使うか(生豆・焙煎度・焙煎時間などの要因も含む)
→抽出される成分に影響を与える
2)どんな水を使うか
→抽出液の味に影響を与える。アルカリ性の水はコーヒーの酸味を中和する。
3)湯の温度(コーヒーと接触している湯温)
→湯温が高くなると抽出量が増える(より濃くなる)。
4)粉の挽き具合
→粒径が細かくなるほど抽出量が増える。特に微粉の影響は大きく注意が必要。
粒度分布の安定性(※)は抽出の安定性に繋がる。
(※)詳細は1級の範囲なので、ここでは挽き目のバラつきが少ないという理解で十分です。
5)湯と粉の接触時間
→長くなるにつれて抽出量が増える。
6)湯と粉の比率
→粉の比率が大きくなるについれてコーヒーの抽出量が増える。
7)撹拌(湯と粉が接触した状態でかき混ぜること)※事前講習会で追加された項目
→回数・強さ・何を使って混ぜるかなどによって、抽出量に影響する。
これらの中でも1)〜2)は比較的安定した要因(同じものを使用すれば味の変化は少ない)であり、3)〜7)は味を変える要因(条件がブレることで味が大きく変化する)として大きく影響します。
つまり、”1)同じコーヒー豆”で”2)同じ水”を使用してコーヒーを淹れたのに以前と味が違う場合は、主に3)〜7)のいずれかか複数の要因が影響していることになります。
同じ味を安定して作り出すためにはこれらの要因を揃えることが必要になり、逆に要因を変えてみることで様々な味を作り出すことも可能になります。これは実際に自分でコーヒーを淹れて試してみることで理解しやすくなると思いますので、ぜひ自宅や会社などで比較してみてください。
2.抽出はどのように進むか
コーヒーの成分の抽出は、コーヒー粉に湯が浸透してから以下のように進みます。
①「粉内部での移動」:粉の内部から表面へ成分が移動する
②「お湯への移行」:表面に移動した成分がお湯に溶け込む
③「ろ過」:成分の溶け込んだお湯がろ過される
それぞれ詳しく説明していきます。
①「粉内部での移動」は、前述の味を変える要因と深く関係しており、以下のようにまとめられる。
・酸味成分の移動は早く、短時間で出きってしまう。
お湯の温度・時間・挽き方の影響をあまり受けない。
・苦味成分の移動は早いものから遅いものまで様々で(酸味よりは遅い)、
遅いものほど渋みを伴った思い口当たりになる。
遅いものほどお湯の温度・時間・挽き方の影響を受けやすい。
・抽出温度を上げることによって、全ての成分の移動量が増える。
・抽出時間を長くすることによって、全ての成分の移動量が増える。
・挽き目を細かくすることによって、全ての成分の移動量が増える。
これらを調整することで濃度や香りを引き出すことができるが、行きすぎると過抽出になり嫌な苦味や雑味が出てしまうため気をつける必要があります。
また、コーヒーの全体的な風味の中でも、まず酸味成分が抽出され、その後徐々に苦味成分が抽出されるという流れになります。
なお、酸味成分はすぐに抽出されてしまうため、酸味自体の成分量の調整は難しいです。その分、抽出時間や湯温などの調整で苦味成分を引き出すことで酸味をマスキングするといった調整ができます。
②「お湯への移行」は粉内部での移動に比べて圧倒的に早く進む。
また、「粉内部での移動」に比べて要因による変化がなく、つまりは教本p33に記載の通り、味を変える要因は「粉の内部から表面への移動に大きく依存している。」ことになります。
③「ろ過」については、次項で詳しく説明していきます。
〜fin〜

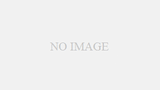
コメント